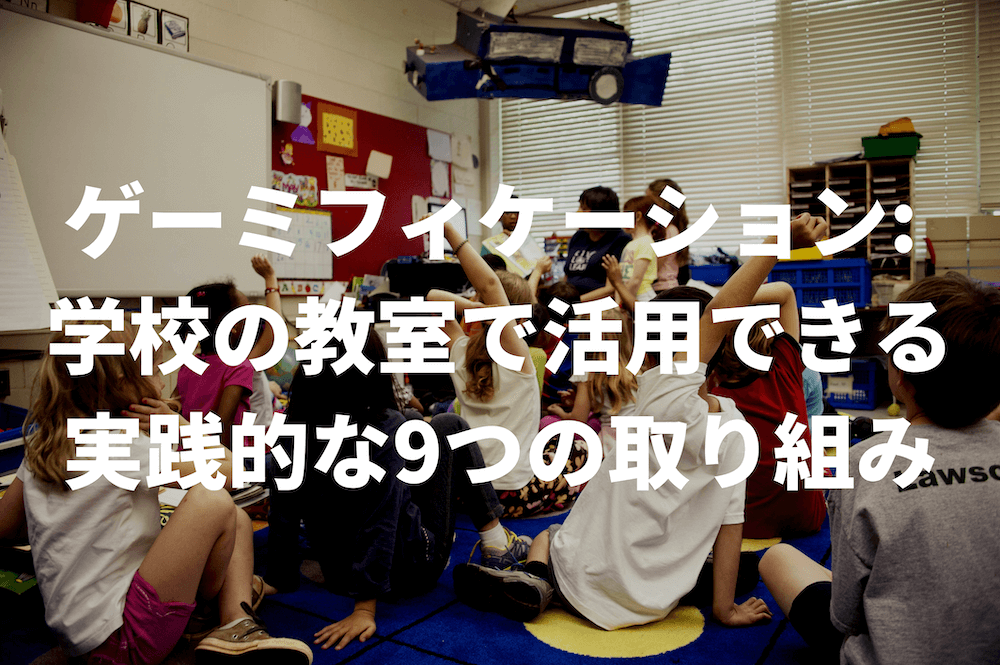みんなゲームが大好きですよね。
電車やバスの中を見渡すと9割以上の人がスマートフォンを触り、半数以上がゲームしていることも珍しくありません。
この記事では、学校の教室で実践できるゲーミフィケーションを紹介していきます。
指導要領に基づいた授業体験より圧倒的に自発性を刺激するゲーム体験、仕組みを実現できれば学習習慣に大幅に寄与できること間違いなしです。
ゲーミフィケーションとは、ゲーム要素をゲーム以外に適用すること
ゲームには、人間が学習するための強力な手段となる多くの要素があります。ゲームは一般的にプレイヤーが問題を解決するように構成されています。ゲームをしていれば自然と問題を解決するスキルを身につけることになります。
多くのゲームは、プレイヤー間のコミュニケーション、協力、競争を促します。没入感の高いゲームの中には、プレイヤーの創造性や想像力を育む豊かなストーリー性を持つものもあります。
大事なことは、ゲームはその設計方法によって、プレイヤーに『教えること』も『試すこと』もできるということです。
ゲームは、教育、学習、評価がセットになった素晴らしいパッケージです。しかもそのサイクルが速いのがゲームの特徴です。学校システムにおける授業では、それぞれの要素はあっても、素早いフィードバックやモチベーションを維持向上させる仕組みはありません。ある程度人力も必要になります。
ゲームの構造的な要素は、いまの世代、ゲームに慣れ親しんできた学習者に適しています。一般にゲーミフィケーションとして知られているこのアプローチは、ストーリーテリング、問題解決、美学、ルール、コラボレーション、競争、報酬システム、フィードバック、試行錯誤による学習などのゲーム要素を、ゲーム以外の状況に追加するものです。すでにマーケティング、トレーニング、消費者主義などの分野で広く実施され、大成功を収めています。
もちろん、教育の分野でもゲーミフィケーションは盛り上がりを見せ始めています。
「Karn Academy」や「すらら」「learningBOX」など、ゲーミフィケーション活用した学習サービスがより多くの教室に普及する可能性は当然のことと言えます。また、教育現場には、独自の「ゲーミフィケーションでデザインされた」学習環境を設計している教育者がちらほら存在します。
ニューヨーク市にある「Quest to Learn」という公立高校では、授業や教室レベルではなく、学習や学校デザインレベルでゲームデザイナーと教育者がカリキュラムを作成しています。
教室におけるゲーミフィケーションの9つの例
ゲームを構成する要素はたくさんありますが、ここでは主要な一つである「報酬」に注目して実際に教室で使えるゲーミフィケーションの事例を紹介していきましょう。生徒が実践すべき重要な行動を特定し、その行動に基づいてゲームや報酬システムを作ります。
1. 正しい議論の進め方に対してポイント付与する
生徒は授業内の議論で、テキストの詳細や結論の根拠を引用する必要があります。その場合、根拠のない回答には1ポイント、根拠が1つある正解には2ポイント、正解+根拠が2つある場合は3ポイントになるようにポイントを付与します
2. 手続き上の目的や学業以外の目的のためのポイント付与
クラスの課題を解決する必要がある場合、例えば、宿題をチェックする時間を短縮したい目的あるとします。このとき、先生に促される前に宿題をチェックできる状態にした生徒には、2ポイントを与えます。
3. 遊び心のあるちょうどよい障壁を作る
障壁の種類には、学業上のもの、行動上のもの、社会的なもの、プライベートなもの、クリエイティブなものなどがあります。ゲーミフィケーションの主要な考え方の1つは、遊び心のある障壁(例えばチャレンジ)を適用することで、励ましのメカニズムを使用することです。励ますために適度な障壁を用意するということですね。
障壁は重要ですが、大事なのは、「遊び心のある」「手を伸ばせばギリギリクリアできそうな」障壁ということです。
つまらない、それやればクリアできるだろうけど正論な障壁では、なかなかモチベーションに影響出るものですので注意しましょう。
4. 教室内に競争を設定する
教室内というと、生徒間での競争を想像すると思いますが違います。競争は、『先生対クラス全員』という構図にします。
生徒は、先生が決めたルールに従わなければなりません。生徒がルールに従えば、クラスは1点を獲得します。生徒がルールに従わなかった場合は、先生が1点を獲得します。
クラスが勝った場合は、休み時間の延長、宿題の量を減らす、自由時間を増やすなど、持続可能な魅力的な報酬を提示します。
先生が勝った場合は、先生の負担が減るもしくは生徒のためになるような活動を設定します。例えば、単元テストや簡単な小テストの作成・採点、ある週のSHRを生徒に運営してもらうなどです。
先生も生徒も最終的にうれしい結果につながるようなルールを決めて、なるべく生徒が勝つように運用します。
5. 各生徒に合わせた絶妙な方法で成績を比較して振り返りを促す
スマホやゲーム機のゲームにおいてミッション修了時には、プレイヤーのパフォーマンスが無数の詳細に分類され、膨大なデータや実績が提供され、自分のパフォーマンスを振り返って記録したり、他の人と比較したりすることができます。
例えば、あるゲームでは、どの目標をどのように達成したかを統計し、その特定のパフォーマンスの「スタイル」に基づいて「バッジ」を割り当て、そのパフォーマンスに関するあらゆる詳細を振り返ることができます。
要するに、生徒毎に目標設定を行い、それを振り返させて、商号など与えるような取り組みです。
これはなかなか難易度が高いので、効果はありますが、生徒自身が目標設定する以前に課題を抱えている場合は、正直あまりおすすめしません。
6. 個性的な生徒には、個性的な報酬を用意する
たとえば、ある教科の授業で5ポイント獲得していた場合、その時間が終わるまで他の教科を進めることができ、10ポイントでスマートフォンで好きなことができ、15ポイントで宿題が免除され、15ポイント以上であれば、その授業自体に出なくても良くなります。
7. レベル、チェックポイント、その他の「進行」方法
複数のクラスでポイントを記録し、100点などの重要な節目に到達したらレベルアップさせ、さらに上達したら、制服着用が原則の場合、私服で登校できるチケットを発行したり、クラス全体の宿題の割合を減らすなど、持続可能な節目の報酬を与えます。
競争心の強い生徒は、クラスや学年で最高のレベルを目指して競い合いますが、これを利用して、レベルの低い生徒を勧誘して、お互いに目標とするスキルを練習させるような問題を作ることができます。レベルの高い子と低い子をお互いの目標を達成させる具体的な事例として、サッカーを例に取ります。レベルが高い子1人とレベルが低い子3人が対抗戦、つまり、1対3になってどちらかがゴール決めたほうが勝ちとします。また、ここまでしなくても、1−3でどちらがボールを奪えるかとしても良いです。こうすると、お互いの難易度設定が適切になっていることが分かりますね。
誰かを教育する活動は、教える側も得られる学びが大きいのでポイントを高くしても良いかもしれません。
8. 成績評価を加点方式にしてエンゲージメントを高める
エンゲージメントとは、ざっくりいうと「深い関わり合いや関係性」を意味します。学習した内容を評価するとき、100点満点を前提としたテストがよく使われますね。100点じゃなくても満点がいくらかというが分かるテストが設定されます。もちろん、生徒は満点がいくらか知っているので実際の点数を見た時、「自分は100点満点中の何点なんだ…」という感覚に陥ります。その点数が100点から離れるほど暗い気持ちになりますね。0点から見て○○点取れたんだ!という前向きな生徒もいますが、たいていはあと何点できなかったんだというネガティブな感情が生まれます。そうではなく、0から評価を始め加点方式にします。すべての課題、スキルの習得、望ましい行動にポイントが与えられ、それらを総合的に評価してランク付け(S〜Fなど)、証明書発行、または任意の報酬を提供します。証明書発行は賞状のような位置付けで目に見えるものがあると嬉しいものです。
9. ポイントや成績の代わりに(またはそれに加えて)、学習バッジを与える
いくつか評価軸を設けると、生徒に対して励ます機会を増やすことができます。ポイントや成績に応じたランク付け以外に、「1週間休まず授業に出席できた」、「テストの成績が3回連続で前より伸びた」、「学習量が先月より増えた」など、昨日、前週、先月よりポジティブな結果に注目すると、励ますポイントが見えてきます。生徒にとっても、「ポイントや成績以外の頑張りが誰かにちゃんと見られている」ことが感じられ、次のアクションはもっと上手くやろうとエンゲージメントを高めることができます。
まとめ
創造性を発揮して、生徒に興味も持たせる仕掛けやコンテンツを用意します。仕掛けが上記のとおりですね。コンテンツは、テストや宿題、課題のことです。「xを求めよ」のような無味乾燥なテストではなく、ミステリー調のテストだったり、学習するポイントを身近な生活に組み込んだ問題を作るなど、興味をもたせるポイントはいくつかあります。
要するに、生徒に興味をもたせる流れを作る必要があるんですね。あなたがなにか物買う時、映画を見に行こうと思えた時、それまでに何度かそれらに接触しているはずですから(テレビCM、情報番組での紹介、ネット広告、YouTube動画の合間の動画広告など)。
もし、あなたが、自己満足のための授業づくりをしたり、自分の承認欲求を満たすために生徒を利用するのはいますぐ辞めたほうがよいです。
生徒たちがポイントを集め、レベルアップし、お互いにもしくは教員と競い合っている間、あなたはデータを収集し、進捗状況を把握し、ルールや報酬、魅力的な問題を調整して、生徒の達成度を高めながら、生徒がポジティブなアクションを取れるような仕組み作りをするんです。
生徒は上達するために必要な活動に熱心に参加するようになり、生徒が納得することで、学校が遊び甲斐のあるゲームになります。